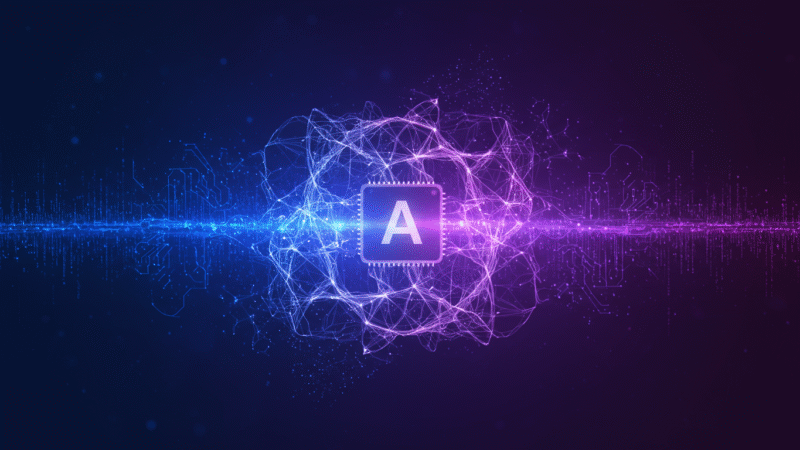
生成AIとは
生成AIは、たくさんのデータを学習して、新しい文章や画像、音楽、動画などを自動で作り出す技術です。これまでのAIは、正解を見つけたり分類したりするのが得意でした。例えば、犬と猫を見分ける、計算問題を解く、メールを迷惑メールかどうか判断するなどです。しかし生成AIは、それに加えて「新しいものを生み出す」ことができます。作文を書いたり、オリジナルの絵を描いたり、音楽を作ったり、プログラムを考えたりと、人間のクリエイティブな活動を助けることができるのです。
普通のAIとの違い
普通のAIは、与えられたデータを見て「これは何か?」と答えたり、「こうなる可能性が高い」と予測したりします。例えば、学校で使う採点アプリが答案を読み取り点数を出すのもAIです。一方で生成AIは、ゼロから何かを作るのが得意です。犬と猫を見分けるだけでなく、「新しい犬の絵を描いて」と頼むと、本当にオリジナルの犬の画像を作ってくれます。分析だけでなく創造もできるのが大きな特徴です。
仕組みはどうなっているの?
生成AIは、人間の脳をまねた「深層学習」という方法を使います。特に「Transformer」という仕組みは文章の意味や文脈を理解するのが得意で、そのおかげで自然で正しい文章を作れます。画像を作るときには、ゲームで競い合うような「GAN」や、最近注目されている「拡散モデル」という仕組みも使われます。これにより本物そっくりの写真やアート作品のような画像を作ることができます。
どこで使われているの?
生成AIは身近なところで活躍しています。学校では、レポートや作文を整えてくれるツールがあり、文化祭のポスターやチラシのデザインにも使えます。趣味では、オリジナルイラストや音楽を作ることも可能です。企業では、会議の要約やプログラムの自動生成、新商品アイデアの提案など、仕事をスピードアップさせています。医療現場でも、病気の診断補助や新薬の開発に役立っています。
気をつけること
便利な生成AIですが、注意点もあります。著作権で守られた作品を知らずに使ってしまうことや、プライバシー情報が含まれてしまうことがあります。また、AIが作った内容が間違っていたり事実でなかったりする場合もあります。AIに全部任せるのではなく、人間がチェックすることが大切です。学校でも、AIで作ったレポートをそのまま提出するのではなく、自分の言葉に直すことが必要です。
これからの未来
生成AIはこれからさらに進化します。文章や画像だけでなく、音声や動画、3Dデータを組み合わせて複雑で面白いものを作れるようになるでしょう。授業中にAIがノートを取ってくれたり、自分専用の参考書を作ってくれたりする時代が来るかもしれません。大切なのはAIに頼りすぎず、正しく活用することです。この技術をどう使うかで、未来が大きく変わるかもしれません。